特別支援教育実践研究学会でのシンポジウム開催報告(2025.10.5)
特別支援教育実践研究学会でのシンポジウム開催報告(2025.10.5)
テーマ「今後の小中学校に求められる特別支援教育の専門性と支援員の役割」
十文字学園女子大学
【シンポジウム企画の趣旨】
我が国の小中学校において特別な支援を必要としている児童生徒の増加が続いています。2007年に文部科学省が特別支援教育の充実の為に導入した特別支援教育支援員制度は、2023年には小中学校に措置された支援員が69,500名となり年々増加しています。このようにインクルーシブ教育の充実が叫ばれる中、小中学校における特別支援教育支援員の役割は大きいと言えます。今回は、小中学校の特別支援教育に関する課題や支援員の専門性、学校現場での具体的な取り組みについて検討し、小中学校における特別支援教育の充実を進めるための支援員の今後の在り方についての課題を整理してみました。
話題提供をお願いした方は、以下の4名です。
1.小池敏英氏(尚絅学院大学教授、「ぴゅあ・さぽーと」理事長)
2.若井広太郎氏(東京家政大学講師)
3.松尾麻衣氏(「ぴゅあ・さぽーと」ラボ所長)
4.大関浩仁氏(小学校校長、全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長)
企画 明官茂(「ぴゅあ・さぽーと」理事)
小池報告「通常学級での学習支援に求められることーインタビュー調査から」
令和4年12月に報告された「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」によれば、学習面または行動面で著しい困難を示す小中学生の割合は8.8%であると報告されている。また、中ら(2019)の研究では、小学2年生から6年生の漢字読みの低成績者の背景要因について検討し、小学2年から4年では特殊音節表記の低成績が背景要因であるのに対して、小学5年と6年では言語性短期記憶の弱さが背景要因であることを指摘した。小学2年から4年では特殊音節表記の低成績が背景要因であるのに対して、小学5年と6年では言語性短期記憶の弱さが背景要因であることを指摘した。これより、学習面での著しい困難に対する支援内容は、学年や児童生徒により多様であり、学習支援員が支援内容を単独で判断することは難しいことを指摘できるとしている。また、支援内容について担任教員が準備する必要があることを指摘できる。
ベテランの特別支援教育コーディネータを対象としたインタビュー調査では、支援内容の準備が大切であるということを確認することができた。また、学習支援員を対象としたインタビュー調査では、支援内容についての情報が十分提供されない場合があるということも確認された。このことから、児童の発達を支える指導の充実を行うためには、支援情報を担任教員が的確に把握し、支援者に伝えることが大切である。
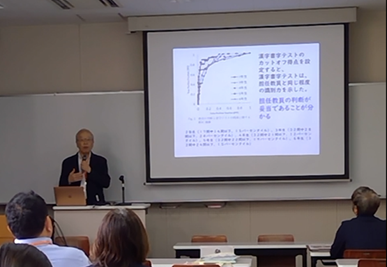
若井報告「小中学校における特別支援教育支援員を取り巻く実態–研修と評価の観点から」
小中学校における特別支援教育支援員(以下、支援員とする)を取り巻く実態と、その成果や課題が複数の調査研究から示されている(荒川ら,2009:松田ら,2022:細谷ら,2014)。その一方で、支援員の評価やサポート体制に言及した研究は少ない。若井(2025)は、関東1都6県の市区町村教育委員会を対象に、支援員に対する研修および支援員の活用に関する評価の実態についての質問紙調査を行った。60件の回答を集計した結果、研修を行っている自治体が73%、活用の評価を行っている自治体が77%であった。また各自治体において支援員のニーズに応じた研修内容の工夫、他機関との連携が行われていることが明らかになった。さらに活用の評価についても、報告書等の間接的な評価に加えて、巡回相談等の視察、支援員へのアンケートといった直接的な評価が行われ、支援員の支援活動を支える評価が行われていることが明らかになった。研修の成果として、支援員の知識や技術の獲得に加えて、悩みの低減、理解の広がり、教員との連携の向上が見られる一方、悩みの低減、教員との連携の向上は課題としても挙げられ、こうした課題を自治体の研修のみで解決することの難しさが示された。さらに二次調査として、数件の自治体にインタビュー調査を行い、各地域の実態に応じた支援員の実務把握とサポート体制についての情報を収集した。
質問紙調査およびインタビュー調査の結果から、以下のことが重要である。
・支援員や学校にニーズに応じた研修機会、内容、方法の工夫
・特に他機関との連携がキーポイント
・研修だけでは改善しきれない課題も存在
・支援員の理解や特別支援教育の知識等、教員へのアプローチも重要
また、今後の展望としては支援員を取り巻く環境の整備として
・直接、現状や意向を伝えられる(相談できる)場や機会の設定
・多様な働き方(勤務時間、給与、対象学級、業務内容)
・ステップアップのための仕組み(昇給、専門性の向上、他職種へのチャレンジ)
が必要であり、そのことで学級、学校、地域の支援力を高める可能性がある。
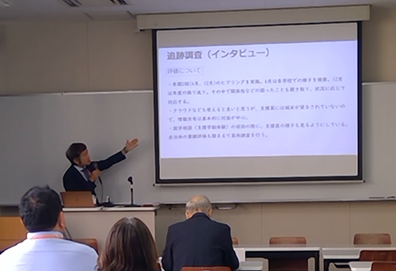
松尾報告「小中学校への支援員配置の実態と課題」
平成19年から全国の小中学校、幼稚園、高等学校に特別支援教育支援員が配置されており、NPO法人「ぴゅあ・さぽーと」ぴゅあさぽーとでは、平成20年から品川区、平成26年から港区、令和2年から渋谷区の特別支援教育支援事業を受託し、幼稚園、小中学校に支援員の配置を行っている。
現在学校には様々な職種が配置されていることもあり、職種同士が人材を取り合う形になり、支援員の獲得が困難になっている現状がある。また、支援員は教員免許などの資格を持っているものもいるが、多くは資格のないものである。支援に入る前に研修を行うなどして、学校での支援がスムーズになるように対応しているが、児童生徒の状況も非常に多様になっており、支援員のスキルでは対応が難しいことも多く生じている。また、支援の方法などについて学校と課題を共有した上で協議して進めたいと感じることも多いが、支援員の配置事業にはそのような協議の機能を持っているわけではないので、学校との連携がうまくいかないことも多い。支援員の方も教員のニーズをくみ取って対応することが難しい場合もあり、学校の望む支援にならない場合もある。
支援員の研修、養成に当たっては、支援スキルを向上させるような内容のものに留まらず、教員のニーズをくみ取った上で、その場で必要な支援を考えられるように養成するという視点が求められていると感じる。
現在実施している研修は以下である。
| 支援員の問題 | 研修の種類 | 研修の形式 |
| 発達特性に関する知識の不足 | 知識を深めるような講座形式 | 短時間で視聴できるような動画視聴 |
| 特別支援教育についての理解不足 | 知識を深めるような講座形式 | 短時間で視聴できるような動画 視聴 |
| 教員や、他職種とのコミュニケー ションの問題、 学校の方針に従わない |
事例検討 | 対面、グループ |
| 悩みを共有したい、聞いてもらいたい |
支援員同士話ができて、 リーダーがリードできるような 内容の座談会 | 対面、オンライン |
| 困りごとへの相談 | 支援に対するアドバイス(心理士などによる) | 支援現場の観察、対面、 オンライン |
また、学校とはどのように連携を取っていけばよいのかについては、
・事例検討では、教員のニーズをくみ取ること、チームの一員として動くことで改善につながるようなケースを設定し、他職種間で協力した上 で支援が成立するということを強調する必要があるのではないか。
・支援員の特徴、強みを評価し、支援員の特徴に合わせた配置をする。
・支援員の強みを評価できる仕組み作りも検討していきたい。

大関報告「小中学校現場の課題と話題提供者への指定討論」
「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議 報告(令和)4年3月」では、教師の専門性向上のための具体的方向性について、採用後10年までの間において特別別支援教育に関する経験をすることについて示された。その一方で、教員不足の問題など様々な学校課題が続くなか、採用後10年までの正規雇用の教員のうち特別支援教育に関する経験(特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、特別支援学級における教科担任、特別支援教育コーディネータ―)が2年以上ある教員は小学校で18.5%・中学校で45%(全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会による令和6年度調査結果より)の状況にある。このような学校現場の実態を踏まえつつ、学級担任と支援員の間における支援対象児童生徒に関する支援内容や具体的方法の共通理解をさらに充実するために有効な手立てについて、それぞれの立場から課題となっている点を突き合わせ、現実的な解決に向けた糸口を紐解く必要があろう。
話題提供者への質問は以下の内容である。
【共 通】 教員との連携に関する課題の具体的な解決策、案
【小池氏】 把握のために学校が活用できるもの、すべきもの
【松尾氏】 支援員の強みを評価するための要素、方法
【若井氏】 機能を評価するための要素、方法

【全体討論・意見交換】
小池氏:より良い支援を行うためには実態を把握することが重要である。またどういう支援が必要かを把握するための専門性が求められている。実態把握や適切な支援を行うことは支援員だけでは難しい、学校全体の取組や専門家の協力が求められている。また、障害の実態によっては、どのように支援するかを短時間で把握できる方法もあるので共有できるとよいのではないか。
松尾氏:例えば、保育士としての勤務経験がある支援員は、子どもの0歳からの発達を知っており、子どもが成功体験を積めるように支援することが可能であったりして、低学年や特別支援学級の配置に適していることが多い。このように、支援員の経験や特性を生かした配置が必要だと感じている。この他にも他害の対応ができる、身体障害のある子どもの支援が可能など、支援員の業務を観察によって洗い出す中で、評価項目を抽出していきたい。
若井氏:現在は、支援システムが脆弱である。明確なガイドラインがないまま、各学校に委ねられているところが大きく文部科学省を中心にシステムを作ることが求められている。担任と支援員だけで全ての課題を解決することは困難であり、はっきり言って学校への丸投げ状態であり文部科学省を中心にシステムを作ることが求められている。学校が全てを把握することは困難であり、担任以外のソーシャルスクールワーカー、スクールカウンセラー、支援員などを含めて学校全体で支援内容を準備する必要がある。時間を調整して学級担任と話し合う時間を校長が作ることが求められている。そのためにも文部科学省がそのようなガイドラインを出す必要がある。
参加者意見A氏:支援員も資質が高い方がいるので、良いロールモデルを作ったらどうか。やってみて良かったこと、実際に子供が変わったことの体験等を示したらどうか。
月に1回くらい支援員を含めて学校全体で振り返りの時間を設定することが大事だと思う。
B氏:学習上又は行動上の課題によって支援の対応が違ってくる。現在は行動上の支援が求められるケースが多いのではないか。また、支援員の中での連携はどうなっているのか。
松尾氏:近年は、学習支援というよりは行動上の問題への支援が求められている。ただ、行動上の問題の背景に学習の困難が隠れていることがあるので、研修には学習支援についての内容も必要と思っている。ただ、支援員はオールマイティーに対応することは難しいので、担任が方針を示すことが基本であると考える。
C氏:支援員のライセンス(初級、中級、上級等)も求められているのではないか。また、専門性のある支援員職の育成も今後大学として取り組みたい課題でもある。

【文責】明官 茂(ぴゅあ・さぽーと)
